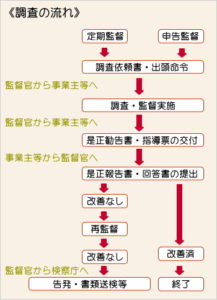改正労働契約法のポイント
改正労働契約法のポイントは?
「労働契約法改正のあらまし」と題するパンフレットが、厚生労働省から出ています。ぜひ、ダウンロードしてください。 ![]() 厚生労働省 「労働契約法改正のあらまし」へ
厚生労働省 「労働契約法改正のあらまし」へ
これは、平成24年8月1日に公布された「労働契約法の一部を改正する法律」に定める労働契約に関する基本的なルール改正について解説したものです。
その中でも、少なからぬ事業主様にとって大きな影響があると思われるのが、「無期労働契約への転換」で、平成25年4月1日から施行されました(上記のパンフレット4~7ページ)。
無期労働契約への転換とは?
使用者と雇用者との契約で雇用期間の定めがあるものを、有期労働契約といい、いわゆる期間社員、契約社員、パートタイマー等は、有期契約の雇用者にあたります。これに対し、雇用期間の定めのない無期労働契約の雇用者は、いわゆる正社員です。ただし、今日、多くの会社は定年制を定めていますから、その意味では、「正社員とは、定年までの有期労働契約の雇用者である」ともいえます。
一方、今回の法改正でいうところの無期労働契約は、文字どおりに「期間の定めのない」雇用契約です。無期労働契約の雇用者に対し、使用者の解雇権限は著しく制限されるのみならず、正社員の定年制を定めていたとしても、ただちには適用できないと解されています。
有期労働契約が通算5年間を超えて反復更新(くりかえし)された場合、有期契約の雇用者が使用者に対して申込を行ったときは、使用者は承諾したものとみなされます。つまり、使用者にその意思がなくとも、雇用者が申込を行えば、それを拒むことはできません。申込があったとき、現に締結している有期労働契約の満了日の翌日から、期間の定めなく労務を提供する無期労働契約があらたに成立することになります。これを、「無期転換ルール」といいます。
解雇できない?正社員よりも有利になる?
有期契約の雇用者が申込を行った後、使用者が現在締結している契約の雇用期間満了日をもって契約関係を終了させようとしたとき、すでに申込の時点で無期契約は成立しています。すると、無期雇用の「解雇」にあたることになり、それが「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合」、使用者の権利濫用として無効となります。また、満了日以前に契約関係を終了させようとすると、それは「契約期間中の解雇」ということになり、通常の解雇よりも厳しい要件が求められるので(労働契約法第17条第1項)、容易に行うことはできません。要するに、無期転換後の雇用者に対し、使用者の権限は著しく制限され、解雇したくても現実にはかなり難しくなります。
それでは、有期契約が「通算5年間を超えて反復更新」していない、したがって無期転換の申込権は発生しない、とするため、その有期雇用者を一時的に直接の雇用関係からはずし、請負や派遣の形態としたとします。それは、いわゆる偽装請負・偽装派遣であり、脱法行為にあたるものとみなされ、それらの期間、有期労働契約は継続していたとされます。
一方、有期契約の更新にあたって、無期転換を申し込まないことを条件とするなど、申込権が発生する前に、雇用者の同意の下、申込権をあらかじめ放棄させればどうでしょう。実例がまだ少ないのですが、こうした行為は、法の趣旨にもとり公序良俗に反するものとして、無効となる可能性が大きいとされています。
いつから、どんな準備が必要?
さて、「無期転換ルール」は、平成25年4月1日から施行とされています。それでは、「通算5年間を超えて反復更新」で申込権が発生するから、「5年以内に雇止め」をすればいいのでしょうか。
確かに、報道等を見ると、「これまで長年更新されてきた人がみな5年以内で契約を打ち切られてしまい、結果的に失業者が増える」といった論調がほとんどのようです。しかし、こうした報道等には、いくつかの大きな誤解があります。
たとえば、平成25年4月1日に3年間の有期契約を締結した雇用者が、同内容のまま契約を更新したとします。その場合、雇用者は、更新契約の発効、すなわち平成28年4月1日以降であれば、いつでも申込ができ(上記のパンフレット4ページを参照)、申込があったとき、もはや使用者は拒むことはできません。
長期安定したサービス提供が求められる事業、たとえば、介護サービス等では複数年にわたる有期契約も少なくないといわれますので、使用者は充分注意する必要があります。
そもそもの話、有期労働契約は、本来、臨時的・一時的な業務に充てるための雇用形態です。しかし、産業構造の転換が続き、不況が長期化するなか、多くの会社では、恒常的な業務のために有期契約で雇用者を雇い入れ、反復更新を重ねた末に雇止めをする、雇用の調整弁とせざるを得なかった実態があります。
今回の法改正が、いわゆる期間工問題やワーキングプア問題などを背景に、方法の適否はさておいて、それらの解決を目指していたことは間違いありません。
近年の解雇事件判例を見ると、雇止めにあたり雇用者が「雇止理由証明書」の交付を会社に求め、その内容が「雇止め基準が不明確で、実質的に無期労働契約と変わるところはなかった」とされ、または最初の更新拒否であっても、「継続雇用への合理的な期待があった」などの理由で、雇止め無効となったケースは少なくありません。
また、改正労働契約法のもう一つの大きな柱として、合理的な理由がなければ雇止めはできないとする「『雇止め法理』の法定化」があります(上記のパンフレット8ページを参照)。
こうしたことから、「まだまだ先の話である」とか、または、「5年以内に雇止めをすれば問題ない」、あるいは、「反復継続していないから、雇止めできる」などの考えは大きな間違いであって、むしろこれを契機として、有期、無期を問わず、就業規則や労働協約、個々の労働契約等を再検討するなど、自らの会社の雇用のあり方を抜本的に見直していくことが不可欠です。